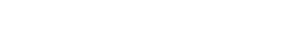ウコン(日局収載)
基源
学名 Curcuma longa L.
【科名】ショウガ科
【生薬名】鬱金 (根茎 日本薬局方収載) 別名 ターメリック
インド原産の多年草です。インドや中国南部など東南アジアで広く栽培されており、日本へは享保年間 (1716-36) に渡来して以来沖縄、九州南部で栽培されています。

根茎は太く、表面には輪状の節があり、鮮褐色を呈します。葉は楕円形で長い柄があり、高さ30〜100cm。花期は秋で、葉間から高さ20cmほどの花茎を立てます。
花穂は多数の淡緑色の苞葉が積み重なり、その中に隠れるように黄色の花を開きます。秋ウコンの名の由来です。
現在、世界には約50種類ものウコン属(Curcuma)の仲間が存在しています。ウコンといっても健康食品の業界では秋ウコン、春ウコン、紫ウコン等の名称が連呼され混乱します。

アキウコン

ハルウコン
中国では、日本でのウコンを姜黄(キョウオウ)、日本での姜黄を鬱金といい、用いられる生薬名が日本と逆になっています。
中医学の生薬分類上、春ウコン(C. aromatica)と秋ウコン(C. longa [ syn. C. domestica ])の根茎を姜黄、塊根を鬱金としていますが、日本に漢方が書物により伝来し普及する過程で、これら情報が混乱し正しく伝わらなかったためとされています

日本薬局方では、C. longaをウコン、C. zedoaria(紫ウコンと称されるもの)をガジュツとして規定し、局方外でC. aromaticaをキョウオウとしています。
鬱金は利胆・芳香性健胃薬として、肝臓炎、胆道炎、胆石症、カタル性黄疸などに用い、また止血・通経薬として吐血、尿血、閉経痛、胸脇部の痛み、腹痛などに応用します。

健胃薬のほか、カレー粉などの食品色素として利用されていますが、最近は健康食品としても人気があるようです。 ウコンの利用は薬用やハーブだけではありません。古くから黄色の染料としてよく知られています。 ウコンで染色した布は虫がつき難いといわれ、インドでは虫の被害から貴重な骨董品や書画などを守るため、この布で包む習慣がありました。
<文献>
牧野和漢薬草大図鑑(北隆館)
日本薬学会薬用植物一覧(web)