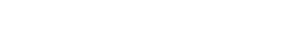雪の結晶がつくられる条件とは?
2024.03.01
雪が積もりました🌨️
水っぽくて、もうすっかり春の雪ですね。
今日はちょっとしか撮れませんでしたが、
【雪の結晶】をお届けいたします。
雪の結晶(雪片)がつくられる条件は、
①気温が低い(氷点下)
②湿度が高い(水分が多いほど結晶が成長しやすい)
③風がない(結晶どうしがぶつかり壊れる恐れがあるため)と言われています💡
まずはじめに、水蒸気が凍る際に水分子どうしがくっつくと、六角形の「氷晶」と呼ばれる氷の結晶がつくられます。その六角形の面に対して、垂直方向(柱状)か水平方向(板状)に成長するかで雪の結晶の形が異なってきます。
形状は121種類に分類され、生成した【気温】と【湿度】によって形が決まります。
特に-10~-20℃(0~-3℃でも生成する)では「板状」になり、この時の湿度が高い場合には、よく見慣れた樹枝状結晶❄️がつくられます。
また、この気温よりも高かったり、低すぎる場合には「柱状」の結晶となります。
同じものは2つとないと言われていますが、成長条件を人工的に制御できれば、見た目の似た結晶(分子レベルでは異なる)を作ることも可能だそうです。
ただし、自然界においては同じものを見つられる見込みが薄いため、そのようなことが言われているそうです🧐
最近ですと、スマホに付けるマクロレンズもありますので、機会があれば観察してみてください👍
1枚目:樹枝六花
2枚目:枝付角板
たぶん…(笑)
水っぽくて、もうすっかり春の雪ですね。
今日はちょっとしか撮れませんでしたが、
【雪の結晶】をお届けいたします。
雪の結晶(雪片)がつくられる条件は、
①気温が低い(氷点下)
②湿度が高い(水分が多いほど結晶が成長しやすい)
③風がない(結晶どうしがぶつかり壊れる恐れがあるため)と言われています💡
まずはじめに、水蒸気が凍る際に水分子どうしがくっつくと、六角形の「氷晶」と呼ばれる氷の結晶がつくられます。その六角形の面に対して、垂直方向(柱状)か水平方向(板状)に成長するかで雪の結晶の形が異なってきます。
形状は121種類に分類され、生成した【気温】と【湿度】によって形が決まります。
特に-10~-20℃(0~-3℃でも生成する)では「板状」になり、この時の湿度が高い場合には、よく見慣れた樹枝状結晶❄️がつくられます。
また、この気温よりも高かったり、低すぎる場合には「柱状」の結晶となります。
同じものは2つとないと言われていますが、成長条件を人工的に制御できれば、見た目の似た結晶(分子レベルでは異なる)を作ることも可能だそうです。
ただし、自然界においては同じものを見つられる見込みが薄いため、そのようなことが言われているそうです🧐
最近ですと、スマホに付けるマクロレンズもありますので、機会があれば観察してみてください👍
1枚目:樹枝六花
2枚目:枝付角板
たぶん…(笑)


ニュースカテゴリ