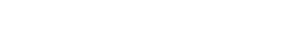ムキタケとツキヨタケの見分け方(キノコ)
2024.10.30


ムキタケ(ガマノホタケ科)
※3枚目の写真はツキヨタケです🔍
晩秋のころ🍂、ブナなどの広葉樹の枯れた幹や倒木などに多数重なって群生します🍄
カサは半円形から腎臓形をし、汚れた黄色または黄褐色で、時に緑や紫色を帯びることがあります。
表面は微細な毛で覆われており、舌触りが悪いため👅、表皮を剥いて食されますが、
この際、表皮の下にはゼラチン層があり、容易に皮を剥くことができるため「ムキタケ」の名を付しています💡
地元では、「カワムケ」とも呼ばれているようです。
また、ゼラチン質でつるっとした食感とその見た目から、「山のフカヒレ」とも言われ親しまれています😋
しかし、汁物にすると、ツルンと熱いまま喉を通りやすく、火傷をしやいことから「ノドヤキ」🔥の別名もあるようです。
生で少し齧ってみたところ、バターのようなほのかな甘みの奥に旨味を感じました!🧈
皆さんは、菌類なのでちゃんと茹でて食べましょう(笑)
カサ裏のヒダは白色で密、短い柄に沿って垂れ下がるように付きます。(垂生)
素晴らしく群生している写真もあったのですが、集合体が苦手な方もいらっしゃると思い、キャンセルしました😅
【ムキタケ】の特徴
①ヒダが密
②カサ表面に毛が生える
③表皮が剝がれやすい
④プルプルした感触
✻ – ✻ – ✻ – ✻ – ✻ – ✻ –✻ – ✻ – ✻ – ✻
見た目もそっくりな「ツキヨタケ」の誤食による中毒事例は、日本で最も多いです⚠️
ブナ林で混生するので注意が必要です。
イルジンSやイルジンMなどの毒成分を含み、食後30分~1時間で嘔吐、下痢、腹痛などの中毒症状を引き起こします。
【ツキヨタケ】の特徴
①ヒダは暗所で発光する、ヒダの間隔が広い
②縦に半分に割ると根本に黒いシミがある
③カサに鱗片が見られる
④柄の根本にツバがある
⑤表皮が剥きづらい
⑥ブヨブヨした感触
などです💡
※3枚目の写真はツキヨタケです🔍
晩秋のころ🍂、ブナなどの広葉樹の枯れた幹や倒木などに多数重なって群生します🍄
カサは半円形から腎臓形をし、汚れた黄色または黄褐色で、時に緑や紫色を帯びることがあります。
表面は微細な毛で覆われており、舌触りが悪いため👅、表皮を剥いて食されますが、
この際、表皮の下にはゼラチン層があり、容易に皮を剥くことができるため「ムキタケ」の名を付しています💡
地元では、「カワムケ」とも呼ばれているようです。
また、ゼラチン質でつるっとした食感とその見た目から、「山のフカヒレ」とも言われ親しまれています😋
しかし、汁物にすると、ツルンと熱いまま喉を通りやすく、火傷をしやいことから「ノドヤキ」🔥の別名もあるようです。
生で少し齧ってみたところ、バターのようなほのかな甘みの奥に旨味を感じました!🧈
皆さんは、菌類なのでちゃんと茹でて食べましょう(笑)
カサ裏のヒダは白色で密、短い柄に沿って垂れ下がるように付きます。(垂生)
素晴らしく群生している写真もあったのですが、集合体が苦手な方もいらっしゃると思い、キャンセルしました😅
【ムキタケ】の特徴
①ヒダが密
②カサ表面に毛が生える
③表皮が剝がれやすい
④プルプルした感触
✻ – ✻ – ✻ – ✻ – ✻ – ✻ –✻ – ✻ – ✻ – ✻
見た目もそっくりな「ツキヨタケ」の誤食による中毒事例は、日本で最も多いです⚠️
ブナ林で混生するので注意が必要です。
イルジンSやイルジンMなどの毒成分を含み、食後30分~1時間で嘔吐、下痢、腹痛などの中毒症状を引き起こします。
【ツキヨタケ】の特徴
①ヒダは暗所で発光する、ヒダの間隔が広い
②縦に半分に割ると根本に黒いシミがある
③カサに鱗片が見られる
④柄の根本にツバがある
⑤表皮が剥きづらい
⑥ブヨブヨした感触
などです💡

ニュースカテゴリ